トークイベントのお知らせ。
長期間&長距離 登山家列伝 #1
『2人の還暦 田中幹也と志水哲也』
〜俺たち生き残りか、死に損ないか〜
二人は高校時代、鷹取山のゲレンデで出会い共に登った同い年。10代後半から30歳前後まで登山に集中したのち、田中は水平方向の冒険に、志水は風景写真の表現に向かって行く。
田中は2013年植村直己冒険賞を受賞し有名になったが、期待され自身の冒険ができなくなったと言う。志水は黒部に憧れ移り住んで活動した26年間が、成功だったか失敗だったか何だったろうかと考えながら生きていると言う。
今年還暦を迎えた二人だが、勝ち取ったものが何かわからないと言う。居場所を求め彷徨っているのではないだろうか。
この国の歩んできた登山の系譜、移り変わりを自身の人生を振り返りながら、戦後に「長期間」「長距離」を目指した特筆すべき登山家冒険家にスポットを当て、その人の特色、目指したものは何だったのか考える。和田城志、細貝栄、竹中昇、栗秋正寿、深谷明、溝江朝臣を紹介する全7回シリーズ。
「どんな優れた表現も砂漠に付けられた足跡以上ではない」誰の言葉だっただろうか? (志水)
●日時
10月1日(水)19:00〜21:00
●会場
The Tribe
東京都千代田区神田小川町2-6-3
東英小川町ビル 地下B1
●定員
先着40名
●参加費
無料
志水哲也(しみず てつや)|1965年、横浜市生まれ
JECC (OB) 、写真家、山岳ガイド
10代後半〜20代に国内、ヨーロッパでのアルパインクライミングの他、南ア、日高、知床などで長期縦走、大井川と黒部川の全支流踏査 (地域研究) を行う。
1997年黒部渓谷の玄関口・宇奈月町 (現 黒部市) に転居。以降2024年まで26年間、黒部、剱岳を題材にした写真集やエッセイ集を多数出版した。その他、日本の秘瀑、日本の世界自然遺産をテーマにした写真集に『日本の幻の滝』(山と渓谷社) 、『水の屋久島』(平凡社) 、『森の白神』(平凡社) の3部作がある。
最近のテレビ出演として、2021年12月は「世界ふしぎ発見」 TBSで屋久島の秘瀑を紹介。2022年は「アドベンチャー魂」 TBS-BSに3回出演。
田中 幹也 (たなか かんや)|1965年、神奈川県生まれ
登攀クラブ蒼氷、地平線会議
10代後半〜20代前半に谷川岳や黒部、甲斐駒ガ岳などの岩壁で四季を通じて合計約200本登る。
20代半ばから中国の奥地やモンゴルの旅。自転車でオーストラリア横断やタイ山岳地帯踏破。
30代〜40代は厳冬カナダの旅に取り組み北部、ロッキー山脈、中央平原、東部ラブラドル半島を訪れ、延べ20回の冬を費やしスキーや徒歩、自転車で合計2万2000キロ踏破。
50代は、天候が荒れるタイミングで冬の津軽の山に通い10年間で合計200日余り吹雪と戯れる。
2013年 植村直己冒険賞受賞
2019年 「クレイジージャーニー」(TBS)出演
2021/2022年 「アドベンチャー魂」(BS-TBS)出演
共著に『目で見る日本登山史』(山と溪谷)、『山と私の対話』(みすず書房)
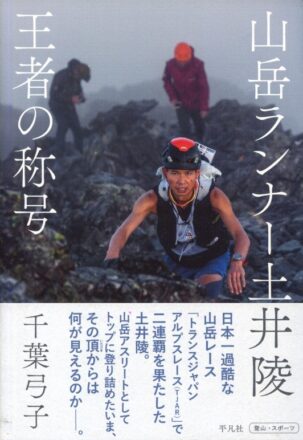
きのう読んだ本。
『山岳ランナー土井陵 王者の称号』(千葉弓子著)
トランス・ジャパン・アルプス・レース(日本海から北アルプス、中央アルプス、南アルプスを縦断して太平洋まで415kmの山岳レース)。
4日17時間33分で完走した選手のはなし。
1日1アルプス。
どう考えてもどうがんばってもオイラには無理!!(笑)
以上。
もし仮に自分にできる実力があったとしたら、じっさいにやっているだろう、、
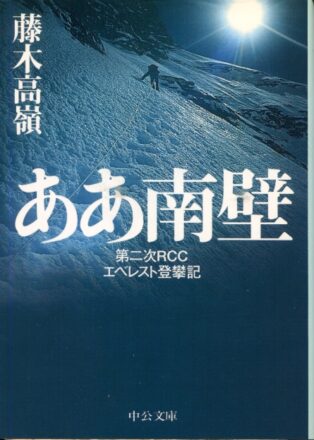
きのう読んだ本。
(1カ月ぶりの読書(笑))
『ああ南壁 第二次RCCエベレスト登攀記』(藤木高嶺著)
まず南壁とはいまでいう南西壁のこと。
1973年秋、当時未踏の南壁(難しいルート)に挑むものの悪天候による時間的制限やそのほかの理由から、東南稜(南壁にくらべると難易度はかなり下がる)からの登頂にきりかわったというはなし。
総額約1億円、隊員48人という今日ではなじみのうすい大遠征隊。
登れることは登れるけれど個性も強いメンバーが集まってできた登山隊だから、もっと人間模様がドロドロしていて過激な口論とかも頻繁に出てくるのかとおもいきや、意外にもおとなしくまとまっている。
すこし拍子抜け。
この本ではさいごにちょこっとしか触れられていないけれど、南壁登攀でがんばった隊員たちのその後がおもしろい。
単独で冬の欧州アルプス三大北壁完登したり、当時としてはめずらしかった2人だけでヒマラヤ6000m7000mの岩壁を登ったり、これまた当時としてはめずらしかった国内で難度の高いアイスクライミングに取り組んだり(←こちらはこの本には出ていない)。
大遠征隊という組織色の濃い登山スタイルに違和感を抱いた体験を踏み台にして、各々があらたなるステージで次なる課題に取り組んでいる。
世の中大半の人たちは違和感を抱いても飲んだ席でぶつくさグチるだけで実践へと昇華できないのだから、やはり彼らは選ばれた人たちだ。
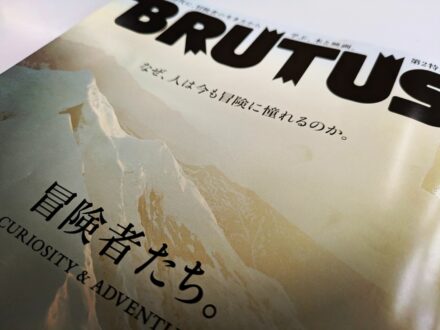
昨夜読んだ雑誌。
冒険者たちを特集した「BRUTUS」最新号。
極地探検、山岳スキー、氷壁登攀、モーターパラグライダー、山岳レース、シーカヤック、洞窟探検と多岐にわたる。
おもったこと以下。
・冒険を実践している人ほど冒険という言葉をデリケートに解釈しようとするのは、自身が死の領域にかぎりなく肉薄したからではないか。
→一般大衆が冒険という言葉を軽々しく用いるのは、やはりリスクに対峙した体験の乏しさからくるのではないだろうか。
・やらずに人生終えるくらいならば結果はどうであれ(失敗すれば死ぬ可能性もある)やってみるという境地に出会える人は、きわめてかぎられるのではないか。
→オイラは失敗すれば死ぬ可能性があることはすべて避けてきた(このあたりはきわめて主感に左右される。個々人による捉え方の振り幅はひじょうに大きい)。
・どのジャンルの冒険者もそれぞれよかったけれどもっとも共感したのは、野村良太さんの冬の北海道分水嶺の単独大縦走のさいごのところ(P34)。
→先月のイベントで、オイラも似たような心境になったのをはなした。おそらく単独で冬の長い縦走をやった多くの人たちも、そうした瞬間を求めて歩いてきたのではないか。
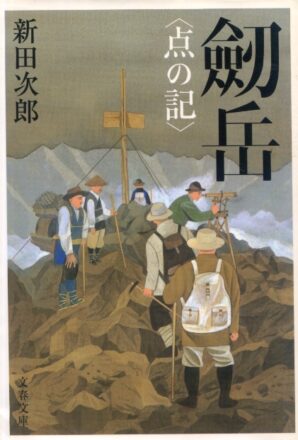
今週読んだ本。
『劔岳〈点の記〉』(新田次郎著)
まずこの本は、史実にたくさんのフィクションを加えた山岳小説。事実とは異なる箇所が多々ある。
(あらすじは調べればいくらでも出てくるので略)
読みながらメモしたこと。
・ライバルの出現(この本の主人公の陸地測量部に対して日本山岳会)はうざいけれど、ライバルがいたからこそ成せたともいえる。
・現場に赴かないお偉いさん(この本では陸軍の上層部)が気になるのは、なによりもメンツ。
・明治時代の装備と情報だったら、オイラは剱岳の頂に立てる自信はない。
ところでオイラは四十代のときに雷鳥沢キャンプ場から剱岳山頂まで1時間半で行ったことあるけれど、先人たちの足跡があってこそ、なによりも鎖やハシゴといった登山道の整備をしてくれる人たちの陰の活動があってこそ成せるのではないだろうか。
この本を読んで、そうあらためて痛感した。
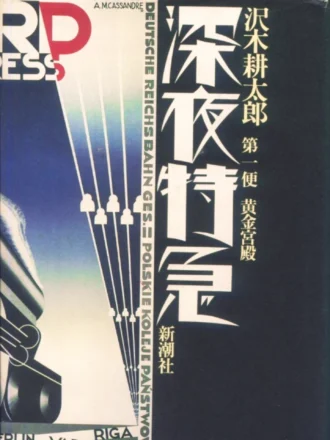
先月再読した本。
(たぶん二十数年ぶり?)
『深夜特急』(沢木耕太郎著)
インドからイギリスまで乗合バスで辿る紀行小説。
さて本との出会いには適期がある。
もうすこし前だったら、もうすこし後だったら、心の琴線に触れることはなかったのではないか。
そうしみじみおもったのがこの本。
『深夜特急』とはじめて出会ったのは、冬のカナダ旅をはじめてしばらく経ってから。
オイラがカナダ北部からロッキー山脈を訪れたころ。
沢木耕太郎とオイラとでは、エリアも旅のスタイルもぜんぜんちがうのに、共感する部分がたくさんあった。
この本でも、旅のはじめの香港では見るもの聞くものすべてに感動するけれど、その後の東南アジアでは香港を越える感動にはなかなか味わえない。
インドに入るとまたあらたな高揚があるけれど、旅の終盤に向かうにつれて、もう昔ほどの感動は起きなくなる。
心楽しかった日々を体験すると、つい次の場所でも期待してしまう。
でも期待が仇となって幻滅してしまったりする。
あの時あの場所であのときの自分だったから、毎日が祭りのようだった。
情熱とはある種の生き物。やがてはさめる。
どこかで切り捨てないと前にすすめない。
オイラの冬のカナダ旅も北部、ロッキー山脈、中央平原と情熱の舞台を移行しながら、いまは厳冬の津軽の猛吹雪を堪能している。
ひとつを切り捨てることによって、あらたなる可能性が芽生えはじめてきた。