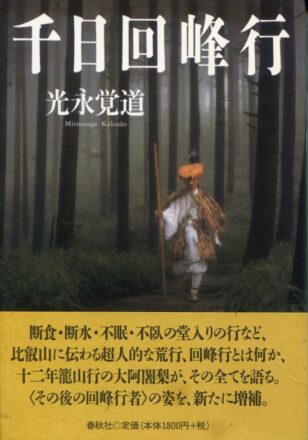
昨夜読んだ本。
『千日回峰行』(光永覚道著)
かんじたこと以下。
・生きてゆくうえで欲は必要。
→欲がなかったら修行をしようとすらおもわない。欲深いのと欲があるのとは異なる。
・行(行動)を深めることによって、心がおだやかになる。
→自分の体験でも厳冬カナダなどで体力的に追い詰められていたにもかかわらず、心は妙にリラックスしていたことが何度かあった。
・空腹がつづくと頭が冴える。
→自分でも断食のまねごとをやったが、精神は研ぎ澄まされる。
「生きて帰ってきただけでもうれしい」(本文より)
千日回峰行に共感する箇所は多々あるが、自分にはまず達成できないだろう。
でも冬のカナダの旅に出会わなかったら、もしかしたら千日回峰行にトライしていたかもしれない。
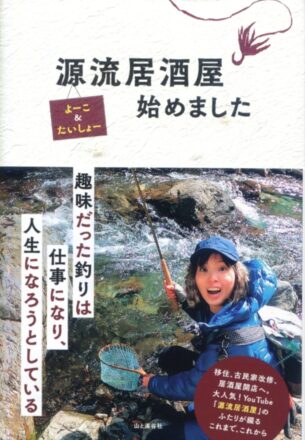
今週読んだ本。
『源流居酒屋始めました』(よーこ&たいしょー著)
山奥の限界集落に大きな古民家を買って自分らおよび仲間とリノベーションして開店する話。
さて田舎暮らしと聞いてすぐに思い浮かぶのは残念ながらネガティブなイメージだ。
旅人として訪れて自然にも土地の人にも魅せられて移住してみたら、冬は雪かきに疲労困憊しコミュニティでは密な人間関係に辟易する。
理想と現実のギャップ。
ところがこの本にはそうした苦労があまり出てこない。
(けっして楽したという意味ではない)
リノベーションしていたらしぜんと協力してくれる仲間があわられて土地の人たちとも仲良くやっている。
なぜ?
この先はあくまでも推測。
もしかしたら、移住前はふつうに組織の一員としてやってきた人のほうが田舎暮らしには向いているのではないか。
人付き合いはしっかりできるし、いろいろ我慢もしてきている。
行動力とアイデアはずば抜けているけれど自由奔放に生きてきた人って、一部から高く評価されるものの合わない人も多い。
バイタリティ溢れ過ぎる人って物事の好き嫌いが激しいから、気にくわないとすぐ言動に出ちゃう。
この本の著者は前者(とおもわれる)。
ちいさなコミュニティでは突出より調和。
今週は偶然べつの人から田舎暮らしのグチを聞かされて、ついそんなふうにおもった。
なおこの本は田舎暮らしの向き不向きといった堅苦しい話じゃない。釣り、狩猟、料理などのびのびとした楽しい話が満載だよ。
きのう読んだ本。
『僕はやっぱり山と人が好き 沢野ひとし対談集』
1980年代半ば戸田直樹、遠藤甲太、大内尚樹、大蔵喜福、江本嘉伸など18人との対談。
80年代半ばといえば、フリークライミングが急速にひろまりはじめた。クライミング雑誌では小川山や城ヶ崎で高難度のフリークライミングが頻繁に登場する。フリークライミングの先行きは明るかった。
一方、80年代半ばまでにエベレストもK2も無酸素登頂される。国内において最大級の奥鐘山西壁でも難ルートが冬季初登される。谷川岳一ノ倉沢衝立岩がフリー化された。アルパインクライミングにおいて大きな課題は一段落する。
60年代70年代にバリバリ活躍していた大学山岳部も社会人山岳会も急速に衰退、低迷がはじまった。
(もちろんごく一部の山岳部や山岳会は精力的に活動していたけれど、あくまでごく一部)
山岳会が元気になるのは飲み会のときくらい。
挑戦だけでなくより楽しさを追求する登山へと移行してゆく。
自分の好みの山もしくは山行スタイルを持ち合わせていない人は、ブーム(話題性?)が落ち着いたとたん路頭に迷ってしまう。
そうした時代において自分の山を見失わず、ユニークな登山や先鋭的な登攀を実践している人たちのはなしである。
昨夜読み終えた本。
『国宝 上』(吉田修一著)
表紙のごとくふたりの歌舞伎俳優のはなし。
(どんなストーリーかはネットでいくらでもでてくるから省略)
はなしが突然飛ぶ。
たとえば冒険の世界では表現力(動画、写真、文章)なのか実力(企画力、精神力、技術、体力)なのかとよくいわれる。
どうしても話上手が目立つ。
冒険は、スポーツのように難度の具体化(数値化)は難しい。
その分野に精通しているといわれる人でも難度をうまく掴めないことが多々ある。
歌舞伎もまた専門家でも評価が難しいのではないか。
血筋(世襲)なのか実力(演技力)なのか。
(もちろん血筋には一般的大衆には想像のつかない縛りも背負っているものも大きいだろう)
そして歌舞伎俳優のふたりの主役がどん底から這いあがろうとするところで、この本の上が終わる。
歌舞伎どころか演劇ですらまったく関心のない自分だけれど、気がついたらのめり込んでいた。
歌舞伎もまた混沌とした世界を試行錯誤しながら夢を求めてすすんでいるのかもしれない。
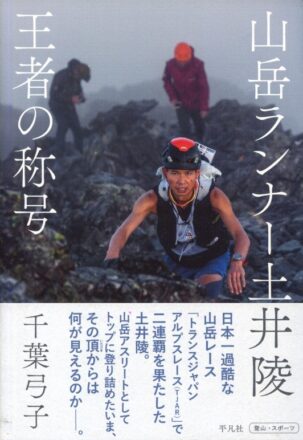
きのう読んだ本。
『山岳ランナー土井陵 王者の称号』(千葉弓子著)
トランス・ジャパン・アルプス・レース(日本海から北アルプス、中央アルプス、南アルプスを縦断して太平洋まで415kmの山岳レース)。
4日17時間33分で完走した選手のはなし。
1日1アルプス。
どう考えてもどうがんばってもオイラには無理!!(笑)
以上。
もし仮に自分にできる実力があったとしたら、じっさいにやっているだろう、、
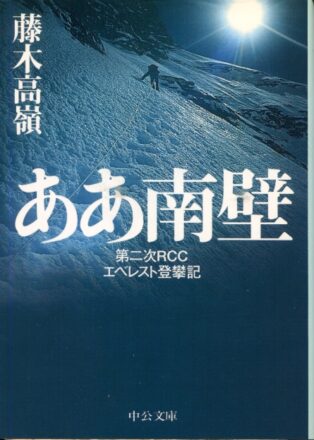
きのう読んだ本。
(1カ月ぶりの読書(笑))
『ああ南壁 第二次RCCエベレスト登攀記』(藤木高嶺著)
まず南壁とはいまでいう南西壁のこと。
1973年秋、当時未踏の南壁(難しいルート)に挑むものの悪天候による時間的制限やそのほかの理由から、東南稜(南壁にくらべると難易度はかなり下がる)からの登頂にきりかわったというはなし。
総額約1億円、隊員48人という今日ではなじみのうすい大遠征隊。
登れることは登れるけれど個性も強いメンバーが集まってできた登山隊だから、もっと人間模様がドロドロしていて過激な口論とかも頻繁に出てくるのかとおもいきや、意外にもおとなしくまとまっている。
すこし拍子抜け。
この本ではさいごにちょこっとしか触れられていないけれど、南壁登攀でがんばった隊員たちのその後がおもしろい。
単独で冬の欧州アルプス三大北壁完登したり、当時としてはめずらしかった2人だけでヒマラヤ6000m7000mの岩壁を登ったり、これまた当時としてはめずらしかった国内で難度の高いアイスクライミングに取り組んだり(←こちらはこの本には出ていない)。
大遠征隊という組織色の濃い登山スタイルに違和感を抱いた体験を踏み台にして、各々があらたなるステージで次なる課題に取り組んでいる。
世の中大半の人たちは違和感を抱いても飲んだ席でぶつくさグチるだけで実践へと昇華できないのだから、やはり彼らは選ばれた人たちだ。