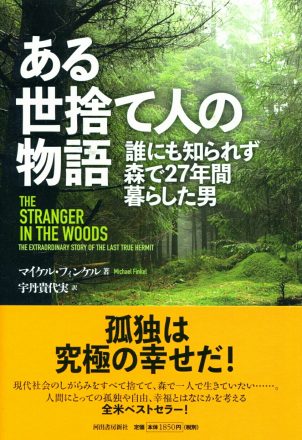
きのう読んだ本。
『ある世捨て人の物語 誰にも知られず森で27年間暮らした男』
アメリカ東海岸北部のメイン州(だいたいニューヨークのすこし北、モントリオールのすこし東)の森に27年間隠れ住んでいた男を取材したルポ。
冬にこのちかくまで行ったことあるけど、ヘタするとマイナス30度くらいまで下がる。
誰とも接することなくひたすらテント生活。
ソローの『森の生活 ウォールデン』を思い浮かべるだろう。
(ソローは小屋だけど、やはりアメリカ東海岸北部のマサチューセッツ州)
ソローは本を出版(インタビューされたのではなく自分で書いた)したわけで、あたりまえっちゃあたりまえだけど外の世界とパイプがある。
まあソローにかぎらず一匹狼とか孤高の人とかは、なんだかんだいって人とも社会とも繋がっているし自分をアピールすることに関しては案外ふつうの人よりうまかったりする。
それに対してこの本の男は27年間、社会とのパイプがまるでない。
興味をひいたのは長年の森の暮らしにおける精神状態である。
森で何をやったのか世間に理解してもらわなくてもかまわない。理解されるためにやったわけではない。
目標も目的も理想も、もはや存在しない。
何々のためにといった理由づけなど不要。
自己表現の必要もない。
永遠の現在にただ存在した。
ただそこにいる。それだけなのだ。
なんだか拍子抜けした感じがしないでもない。
だって何かをやるにあたって、どうしてもその先に何かを期待してしまうから。
究極の悟りとは、悟ることが何もなくなることなのかもしれない。
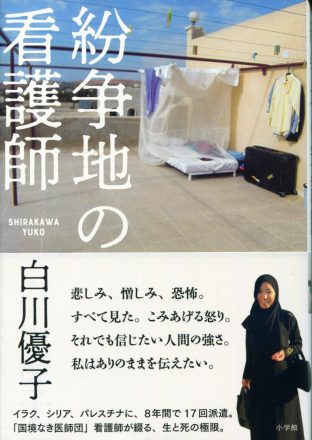
『紛争地の看護師』(白川優子著)
国境なき医師団の看護師としてイラク、シリア、パレスチナ、南スーダン、イエメンなど8年間で17回。
いずれも過酷な医療現場ばかり。
それにしてもよく精神も身体ももつものだ。
それにしてもよく途中で投げ出さずにやってこれたものだ。
もっと楽な生き方だってあるんじゃないの?
それに引きかえ自分はこれまでいったい何をやっていたのだろうか。
自分にはいったい何ができるのだろうか。
登山もクライミングも冒険も命がかかっとるいうけれど、しょせんはごっこの域を出ない平和ボケした遊びに過ぎなくねえ?
この著者の訴えようとしている激戦地における悲惨な現状よりも、なぜかそんなことばかり思ってしまった。
誕生日のつぎの日に読んだ一冊。

『かかわると面倒くさい人』(榎本博明著)
いるいるいるいるいるいるいるいるねーッ!!
山小屋とか民宿とかにたむろすクソ・ガイドやら名物じじいやらヘタレ・オヤジやら。
できるアピールができないアピールになっとることに、まるで気づいてない。
能力が低い人は技能が低いだけでなく、能力の低さに気づく能力も低い。
この本では、そういう人とは適度な距離感を保つことが解決策だといっている。
オイラはもう一歩踏み込んでみたい。
距離を置くだけでなく観察してみる。
野生のクマだってテントのまわりでうろうろされたら恐怖と不快しかないけれど、遠くから双眼鏡で眺めるぶんには雄大な自然の印象深いワンシーンとなる。
かかわると面倒くさい人も、いなくなってしまうと案外寂しくなってしまったりするものだ。
適度な距離感と遊び心はつねに意識したい。
面倒くささとは、ひとつの味でもあるのだろう。

昨夜、やっと読み終えた本。
『漂流』(角幡唯介著)
1994年に漁船が沈没して救命イカダで37日間漂流。
フィリピンのミンダナオ島で発見されるも、8年後にふたたび海に出たままいまだに行方不明。
二度も行方不明となったひとりのマグロ漁師の生きざまを追ったルポ。
400ページを越える。
マグロ漁が金になったのはもう過去の話、みたいな水産業界の説明はめんどくさいから読み飛ばす。
興味をひかれたのはこの漁師の世界観、というよりも死生観。
少なくとも一般大衆にくらべれば、死というものが日常にきわめて密接している。
死の捉え方が超越している。
「海に生きる」とは、死をもふくめたリスクをしぜんに受け入れることなのではないだろうか。
この漁師の生きざまにここまで迫れたのは、この本の著者が言葉だけで処理する頭でっかちんノンフィクション作家ではなく、自身もしばしばプチ行方不明にすらなる実体験型ノンフィクション作家だからであろう。
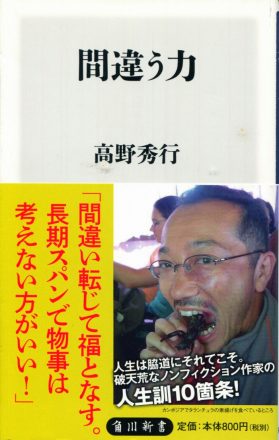
昨夜読んだ本。
『間違う力』(高野秀行著)
アフリカでの謎の怪獣探しやミャンマー北部の麻薬地帯長期滞在を行ってきたノンフィクション作家のこれまでの奇跡を、人生訓10カ条にまとめたもの。
とにかく早大探検部出身のこの著者は、何でもあり。
いやだって、、、
自由を求めて山とか旅とかやっとるのに、教条主義を押しつけてくる輩が少なくないから。
サンダルで夏の北アルプスを歩いてはいけません、自転車で雪の上を走ってはいけません、はじめてのスキーで長期縦走をやってはいけません、運動靴で雪山に行ってはいけません、台風直撃のときに山でキャンプしてはいけません、冬型が強まったときに東北の日本海側の山に行ってはいけません。
あれダメこれダメそれもダメ、、、
この著者は、基本などはなから無視していきなり応用から入る。
だいたい基本をきっちりやっていたら実践に移る前に人生が終わる。
この本に書いてあることが役に立つかどうかはさておき、まずはやったもん勝ちという著者の姿勢は読んでいて気分がスカッとする。
いくら猛練習を積んでも絶対に試合に出ない野球選手に価値はない、と言いきる。

書評を書いた。
厳冬の真っ暗闇のグリーンランド北部の80日間のひとり旅を綴った『極夜行』(角幡唯介著)。
事情に明るい人が見ても発想も行動も特化しとる旅だけれど、一般大衆にも共感できるように噛み砕いて書くのがこの著者の手法である。
難解な最先端の化学の研究を、化学反応式を用いずにわかりやすく説明して、なおかつ楽しめるかんじ。
深い行動ができて書けるのが角幡唯介。
そういう本の書評だ。