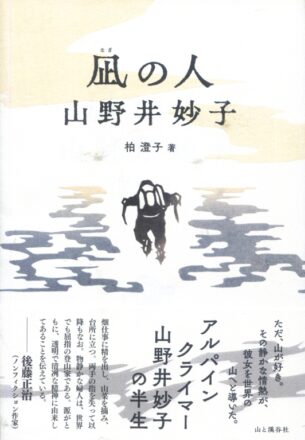
昨夜読んだ本。
『凪(なぎ)の人 山野井妙子』(柏澄子著)
かんじたこと以下。
・表紙がいい
→表紙をとりはずしてひろげてみるともっといい。激しい登攀とおだやかな日常と。
・凍傷で指を切断してからのほうがクライミングがうまくなっている
→指がある人よりも登れたりする。家事に関しては、指がちゃんとある自称・主婦のベテランより遥かにきちんとこなす。
・山行歴のさいごが南アルプスの南部というのもいい
→古希をむかえ、これからどんな山行がならぶのだろう。おそらく潮どきといった概念すらないのかもしれない。

2月もきょうで終わり。
1カ月の三分の二は、寒波襲来の津軽の山で過ごす。
凍ったテントのなかであれこれ考える。
厳冬アラスカの山で合計846日(16冬で)過ごした栗秋正寿の世界をおもった。
オイラごときの拙い経験であれこれ発信(表現)してしまっていいのだろうか。
いやだからこそそうしたジレンマみたいなおもいを発信(表現)したい。
今月はあっという間だった。
◇
画像は、今季最強寒波襲来の津軽。

今回も行ってよかった。
とつぜんの腰痛悪化で動けなくなることを予測して、何かあっても生き延びれるように、10日分の食糧と燃料を担いで入山する。
連日つづく大雪。下山した日の積雪4メートルを越えていた。
街でも例年にくらべて倍ちかい雪の量。
そして冬の津軽の山ではめったにない快晴にめぐりあう。
ごくたまにしか晴れないからいい。
冬の津軽の山は10年間で200日ちかく入山している。山の頂には数回立った。

30年ぶりか40年ぶりかで来た。
若いころロープなしで登っていた自分が信じられない。
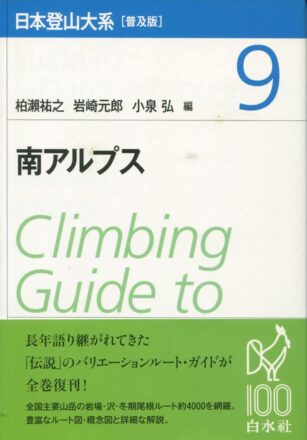
昨夜読んだ本。
(ひさびさに再読)
『日本登山大系 南アルプス』
南アルプスは甲斐駒ヶ岳の岩壁の登攀を除けば1回しか行ったことがない。
中学生のときの夏、ひとりでテントで甲斐駒ヶ岳から聖岳までの縦走。
縦走そのものは歩けば目的地に着く。
登山道を行くだけで道に迷うことはない。
むずかしさはない。
(昨今のYouTubeやSNSが大げさすぎる)
その縦走で印象深かったのは、南アルプス南部(静岡県北部)。
林道の長さ、人里までの遠さ、つまり「山の奥深さ」だった。
三十代のころ、冬のカナダのロッキー山脈の長期縦走をテーマにとりくんでいたときも、アプローチの長い、つまり林道の長いコースどりをしぜんに選択していた。
五十代後半になった最近は、やっていることはスゴいわりに一般的に知られていない登山家の足跡を調べている。
南アルプス南部(静岡県北部)を舞台に、ボリュームある記録がいくつかある。
代表的なものに、、
ウェットスーツ製の渓流足袋をかつぎ上げ厳冬の大井川源流の沢登り。アプローチの長さから1本の沢だけで10日から2週間費やす。
ほかにもいろいろあるが諸事情により割愛。
中学生のときの数日間の体験が「山の奥深さ」というひとつのキーワードとして、自身の登山の価値基準となって定着しちゃったのかもしれない。
本を読み返しながらそんなことをおもった。