
昨夜はクライミングギャラリーThe Tribeにて「冒険とは、旅とはⅢ」(荻田泰永×田中幹也)のイベント。
冬のカナダの旅がメインなのだけれど、自分の場合はどうしてもクライミングから旅へ移行の話をしないと繋がらない。
クライミングは楽しかった。一緒に登った人も個性豊かでおもしろかった。
でも、自分にはクライミングとはちがった別の世界があるのではないかという違和感がついてまわった。
クライミングから旅への移行は、いまだにうまく整理できていない。
この先も自身に問いかけていきたい。
これからも何をめざしているのかわからない旅をつづけていきたい。
クライミングの世界でかんじたいいようのない閉塞感は、旅の世界ではあまりない。
要所で、舞台が岩壁登攀や自転車旅や大雪原の冒険なのに夜のバンコクやタイの女にハマる話を盛り込まざるを得なかった(固人名は出さなかったよ(笑))
なお荻田さんは、2011年冬から初夏にかけて角幡唯介と歩いたカナダ北東部のレゾリュート〜ジョアヘブン〜ベイカーレイク、1600km、103日間。
話がまとまっていてうまい。
なぜそこを歩いたのか、そしてそのルート周辺をとりまく19世紀の北西航路の航海の話が盛り込まれていてひじょうに興味深かった。
ふたりとも氷の上を歩きながら、荻田さんには荻田さんの世界が、自分には自分の世界がある。
(画像のカナダ地図の線は、自分の旅の軌跡)
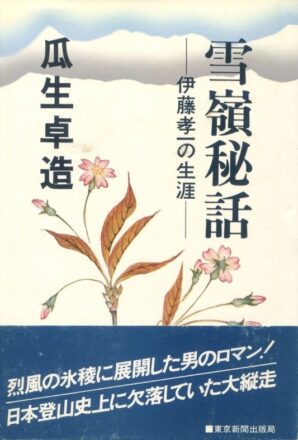
昨夜読んだ本。
『雪嶺秘話 伊藤孝一の生涯』(瓜生卓造著)
たとえば実力があってもその分野を牛耳っている人に気に入られないと黙殺されてしまったりすることはよくある。
この本は、日本登山史から黙殺同様にあつかわれた二つの長大な縦走記録を柱にその人と背景を掘り起こしたもの。
この主人公の伊藤孝一は大学山岳部(旧制高校旅行部)とも町の山岳会とも関わりがない。
強いて肩書をいうならば資産家が、以下の記録をつくった。
・1923年(大正12年)3月5日〜22日
黒部横断、芦峅寺〜立山温泉〜室堂〜立山・雄山〜立山温泉〜鳶山〜ヌクイ谷〜黒部川・平〜針ノ木峠〜大町
伊藤孝一ほか芦峅寺のガイド含め合計22人
・1924年(大正13年)4月1日〜23日
真川〜北ノ俣岳〜黒部五郎岳(鷲羽岳、水晶岳、祖父岳にも登頂)〜双六岳〜槍ガ岳〜上高地〜徳本峠〜島々
伊藤孝一ほか芦峅寺のガイド含め合計33人
この時代をみると、各大学山岳部がようやく冬の槍穂高岳のピークを単体で登頂に成功しているにとどまる。
また伊藤孝一は冬の長い縦走に成功しただけでなく映画撮影も大がかりに行っている。
「伊藤は冬の縦走で日本山岳会の鼻をあかした」(本文より)

昨夜読んだ本。
『人類初の南極越冬船 ベルジカ号の記録』(ジュリアン・サンクトン著)
19世紀のおわり、南極探検に向った船が氷に閉じ込めらて極夜を過ごした話。
(南極点も北極点も到達される前)
メモしたこと以下。
・想像していたほど壮絶ではなかった。隊員の大半が気が狂って半数以上が死んだのかとおもいきや、ほとんどが生還している(もちろん犠牲者はいる)。
→越冬できるだけの食糧、燃料があったこと。船という住処が確保されていること。衣食住がひとまず足りていると、危機感は大幅に軽減される。というのはオイラの経験でもじっさいにあった。
・危機に瀕してもマスコミ受けを意識している。
→出資者あってこそ成り立つ当時の探検。一般大衆の目を意識するのは当然の帰結。いまの時代の個人の趣味の探検とは背景が異なる。
・生還した隊員のその後がおもしろい。ある隊員はこの体験を生かしてのちに南極点到達を果たす。べつの隊員は怪しげなビジネス(?)で詐欺罪で起訴されて刑務所に入る。
→かたや成功者、こなた転落人生、という単純なはなしともちがう気がする。夢の実現と人を騙すことって、どこか水面下で繋がっていないか。大胆さと人を動かす力、そして斬新なアイデア。この極地探検家と詐欺師コンビは、船が氷に閉じ込められて多くの隊員が意気消沈しているなかでもっとも意欲的に解決策を生み出して脱出成功に導いている。
学生時代の夢だった。
三十歳くらいを過ぎてそうポツリとつぶやく人は、どの分野にもいる。
でもほんとうのところはどうなのだろう。
もともとの情熱がしょせんはそこまでだったのではないか。
実力だって自身がおもうほどにはなかったのではないか。
だから学生時代の夢だったで終っちゃうのだろう。

昨夜読んだ本。
『剱沢幻視行 山恋いの記』(和田城志著)
(何度めかの再読)
この著者は、冬の黒部横断を若いときから約五十歳まで30回行っている。
剱岳・八ツ峰北面の雪稜や剱沢大滝など、隔絶されたエリアにおける難度の高い登攀をも組み込んでいる。
二十代三十代で力のかぎり登ろうぜと語る人はいるけれど、多くは四十歳くらいから急におとなしくなっちゃう。
30年ちかくにわたり毎冬黒部横断を実践する人、もしかしたらもうあらわれないかもしれない。
オイラ個人の体験からすると、冬の長い縦走ってどうがんばっても三十代半ばが限界だった。