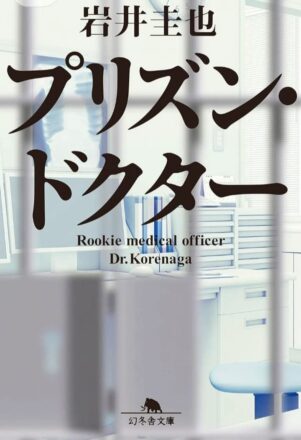
昨夜、読んだ本。
『プリズン・ドクター』(岩井圭也著)
(おおたわ史絵の『プリズン・ドクター』とはちゃうで)
こちらは医療小説。
舞台は、刑務所における医療。
でも背骨の部分は、看守の爆走する正義感の恐ろしさ。
「悪の自覚がある人間は、自分の罪の重さを承知している。しかし正義に酔いしれた人間には、自分が犯した正義感さえ見えていない」(本文より)
自信満々にSNSで人を叩く、「自称・正義の人」がふっと頭に浮かんだ。
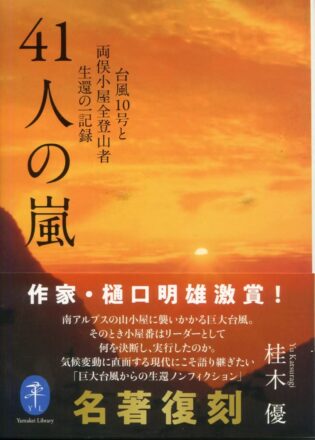
昨夜一気に読んだ本。
『41人の嵐 台風10号と両俣小屋全登山者生還の一記録』(桂木優著)
メモしたこと以下。
・危機に瀕したさいの解決策に正解はない。
→自分としては、直感的にいちばんはじめに頭に思い浮かんだことを重視している。
・危機に瀕したさいに問われるものって、いったい何なのだろう。
→はたして経験は生きるのか。あるいは経験は邪魔になるのか。
・主人公の小屋番はもちろんだけれど、学生たちもかなりしっかりしている。
→体育会系の良き面、チームワーク。
もし仮に自分が小屋番だったら、あるいは学生のひとりだったとしたら、もしかしたら全滅に導いていたのか、それとももっと効率よく撤退できたのか。
あれこれシミュレーションしてみると、自身の短所がみえてきたりする。

昨夜は、本の紹介(「二十歳の原点」(高野悦子著))のミニ・イベント。
うまく話せたかどうかはわからない。来てくれた人たちを楽しませることができたかどうかはわからない。
ただ自身のなかで悶々としていた十代のころのことが、すこしずつ整理されてきたのはたしかだ。
生まれてきたからには、何か大きなことをやりたい。でも踏み込む勇気がない。だって山では失敗したらすぐに死んじゃう。でもやっぱり今のままじゃダメだ。
そういう思いを毎日のようにくり返してきた、自分の十代のころ。
あのころはただ出口をさがしていた。
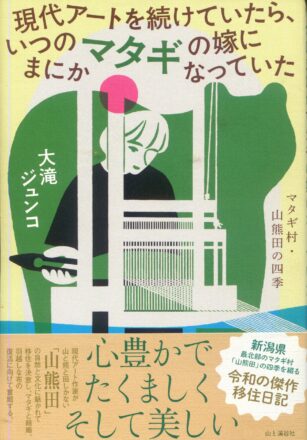
一昨日、一気に読んだ本。
『現代アートを続けていたら、いつのまにかマタギの嫁になっていた マタギ村・山熊田の四季』(大滝ジュンコ著)
まずオイラはマタギにも狩猟にも伝統にも限界集落にも、ぜんぜん興味ない。
新潟県最北部という、やや隔絶感のある土地柄に惹かれた。
夏は、猛暑にくわえてメジロやらアブやら吸血系の猛攻撃。
冬は、日本海側に面した山沿い特有の悪天候。そして名物のドスの効いた大雪。
ここ何年か年に数回新潟に通っている。今冬は7回。
(山熊田のある新潟県北部はまだ訪れていない)
この本の舞台となる山熊田をかこむ山や自然、空気に触れてみたくなった。
行くなら厳冬季の猛吹雪の日がいい、誰にも知られずにひとりで。
自然の猛威に肉薄してときに負傷して次の段階で土地の人たち、というのがオイラのこれまでのやや隔絶感のある土地との接し方だった。
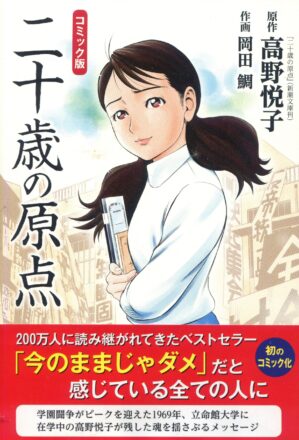
昨夜読んだ本。
『コミック版 二十歳の原点』(高野悦子原作)
オイラは十代のころから、今のままじゃダメっておもっていた。
いらい40年ずっとずっとそのおもいは消えない。
おそらく生きているかぎり、今のままじゃダメ、そして何かを変えたいというおもいが燻りつづけるのだろう。
なおコミック版はハッピーエンドだけれど、シリアスな終焉の原作のほうがいいな。