昨今の登山界、場違いともおもわせる人がたくさん出没している。
山などほとんど行ったことないような(ツアー登山が中止にならないていどの山行しか経験ない)人たち。
でも発生してきて生存しているということは、何か意味はあるのだろう。
その意味について考えてみるのもおもしろいかもしれない。
一昨日、高尾山でのマン・ウォッチング。
高価な登山靴やウエアで身をかためた、いわゆるお手本の格好をした人ほど、映画『八甲田山 死の彷徨』みたいに生と死の分岐点をおもわせる歩き方をしていたよ。
ヤンキーが街からそのままやって来ちゃったみたいな人のほうが、元気で楽しそうに歩いていたよ。
えっ、軽装でもし何かあったらどうするのかって?
想定外のときって案外ちゃらちゃら組のほうが強かったりする。

たぶん自分がやっていることは一般的な登山とは異なるのだろう。
降雪量が多いとおもわれるとき(寒波襲来など)にもっとも雪が溜まりそうなところ(森林限界上よりも樹林帯)をめざす。
そして、そこから帰る。
ハマるからドラマが生まれる。
山も旅も自由にやっていい。
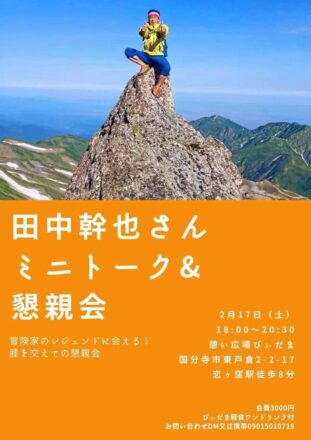
国分寺「びぃだま」トークイベントのお知らせ。
中学生のとき丹沢や南アルプスをひとりで歩いていた。
いまみたいに山の景色の記憶は皆無。
山でいちばんの楽しみは、ほかの登山者から山の話を聞くことだった。
まだ丹沢しか知らなかった自分にとって、どんな山の話も新鮮だった。
山の難度という概念すらなかったあのころ。
山も人も純粋に輝いていた。
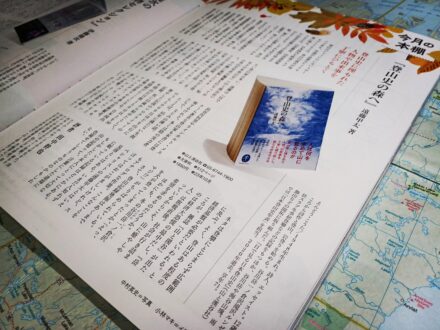
書評を書いた。
『ヤマケイ文庫 登山史の森へ』(遠藤甲太著)
書かれていることだけがすべてではない。
多くの人は、活字にしないと反応しない。
多くの人は、活字にしたとたん鵜呑みにする。
たいせつな記憶って、言葉にしたとたん色褪せてしまう。
あの世まで持っていきたい思い出がある。
眠っている(埋もれている)記録、あってもいい。
山の思い出、すべてを語らなくってもいい。
以上、書評を書きながらメモしたこと。
この本は、一般的な登山者には馴染みのうすい登山(登攀)記録を掘り出して、ときにユーモアをまじえて解説したもの。