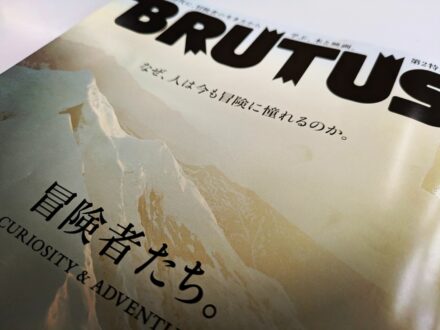
昨夜読んだ雑誌。
冒険者たちを特集した「BRUTUS」最新号。
極地探検、山岳スキー、氷壁登攀、モーターパラグライダー、山岳レース、シーカヤック、洞窟探検と多岐にわたる。
おもったこと以下。
・冒険を実践している人ほど冒険という言葉をデリケートに解釈しようとするのは、自身が死の領域にかぎりなく肉薄したからではないか。
→一般大衆が冒険という言葉を軽々しく用いるのは、やはりリスクに対峙した体験の乏しさからくるのではないだろうか。
・やらずに人生終えるくらいならば結果はどうであれ(失敗すれば死ぬ可能性もある)やってみるという境地に出会える人は、きわめてかぎられるのではないか。
→オイラは失敗すれば死ぬ可能性があることはすべて避けてきた(このあたりはきわめて主感に左右される。個々人による捉え方の振り幅はひじょうに大きい)。
・どのジャンルの冒険者もそれぞれよかったけれどもっとも共感したのは、野村良太さんの冬の北海道分水嶺の単独大縦走のさいごのところ(P34)。
→先月のイベントで、オイラも似たような心境になったのをはなした。おそらく単独で冬の長い縦走をやった多くの人たちも、そうした瞬間を求めて歩いてきたのではないか。
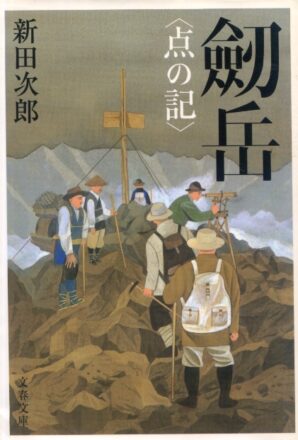
今週読んだ本。
『劔岳〈点の記〉』(新田次郎著)
まずこの本は、史実にたくさんのフィクションを加えた山岳小説。事実とは異なる箇所が多々ある。
(あらすじは調べればいくらでも出てくるので略)
読みながらメモしたこと。
・ライバルの出現(この本の主人公の陸地測量部に対して日本山岳会)はうざいけれど、ライバルがいたからこそ成せたともいえる。
・現場に赴かないお偉いさん(この本では陸軍の上層部)が気になるのは、なによりもメンツ。
・明治時代の装備と情報だったら、オイラは剱岳の頂に立てる自信はない。
ところでオイラは四十代のときに雷鳥沢キャンプ場から剱岳山頂まで1時間半で行ったことあるけれど、先人たちの足跡があってこそ、なによりも鎖やハシゴといった登山道の整備をしてくれる人たちの陰の活動があってこそ成せるのではないだろうか。
この本を読んで、そうあらためて痛感した。
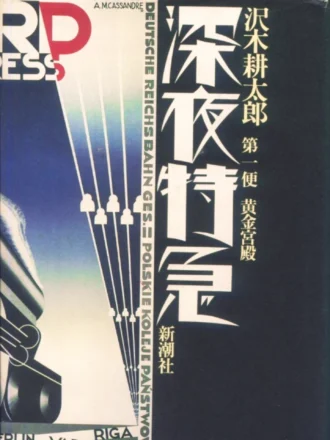
先月再読した本。
(たぶん二十数年ぶり?)
『深夜特急』(沢木耕太郎著)
インドからイギリスまで乗合バスで辿る紀行小説。
さて本との出会いには適期がある。
もうすこし前だったら、もうすこし後だったら、心の琴線に触れることはなかったのではないか。
そうしみじみおもったのがこの本。
『深夜特急』とはじめて出会ったのは、冬のカナダ旅をはじめてしばらく経ってから。
オイラがカナダ北部からロッキー山脈を訪れたころ。
沢木耕太郎とオイラとでは、エリアも旅のスタイルもぜんぜんちがうのに、共感する部分がたくさんあった。
この本でも、旅のはじめの香港では見るもの聞くものすべてに感動するけれど、その後の東南アジアでは香港を越える感動にはなかなか味わえない。
インドに入るとまたあらたな高揚があるけれど、旅の終盤に向かうにつれて、もう昔ほどの感動は起きなくなる。
心楽しかった日々を体験すると、つい次の場所でも期待してしまう。
でも期待が仇となって幻滅してしまったりする。
あの時あの場所であのときの自分だったから、毎日が祭りのようだった。
情熱とはある種の生き物。やがてはさめる。
どこかで切り捨てないと前にすすめない。
オイラの冬のカナダ旅も北部、ロッキー山脈、中央平原と情熱の舞台を移行しながら、いまは厳冬の津軽の猛吹雪を堪能している。
ひとつを切り捨てることによって、あらたなる可能性が芽生えはじめてきた。