表舞台から突き落とされるのはたしかに悲惨。
でも俺が俺がといいつつ表舞台とは無縁でちっぽけなコミュニティで人生の幕を閉じるほうがもっと悲惨だ。

30年ぶりか40年ぶりかで来た。
若いころロープなしで登っていた自分が信じられない。
やっぱり自分のやっとる山や旅が、一般大衆に受け入れられてしまったら成り立たなくなるよな。
いっぽうで自分のやっとる山や旅が、誰からも共感されなくなってもこれまた成り立たなくなるだろうな。
そんな微妙な立ち位置が好き。
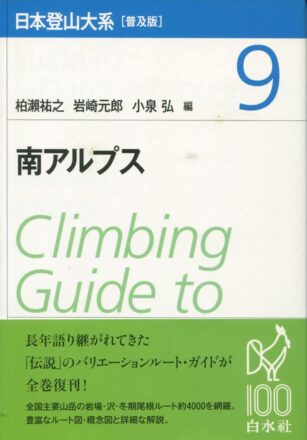
昨夜読んだ本。
(ひさびさに再読)
『日本登山大系 南アルプス』
南アルプスは甲斐駒ヶ岳の岩壁の登攀を除けば1回しか行ったことがない。
中学生のときの夏、ひとりでテントで甲斐駒ヶ岳から聖岳までの縦走。
縦走そのものは歩けば目的地に着く。
登山道を行くだけで道に迷うことはない。
むずかしさはない。
(昨今のYouTubeやSNSが大げさすぎる)
その縦走で印象深かったのは、南アルプス南部(静岡県北部)。
林道の長さ、人里までの遠さ、つまり「山の奥深さ」だった。
三十代のころ、冬のカナダのロッキー山脈の長期縦走をテーマにとりくんでいたときも、アプローチの長い、つまり林道の長いコースどりをしぜんに選択していた。
五十代後半になった最近は、やっていることはスゴいわりに一般的に知られていない登山家の足跡を調べている。
南アルプス南部(静岡県北部)を舞台に、ボリュームある記録がいくつかある。
代表的なものに、、
ウェットスーツ製の渓流足袋をかつぎ上げ厳冬の大井川源流の沢登り。アプローチの長さから1本の沢だけで10日から2週間費やす。
ほかにもいろいろあるが諸事情により割愛。
中学生のときの数日間の体験が「山の奥深さ」というひとつのキーワードとして、自身の登山の価値基準となって定着しちゃったのかもしれない。
本を読み返しながらそんなことをおもった。
ちょこっとかじっただけの体験で、上から目線で論じる人っていったい何なんだろう。
死ぬようなヤバい目にも遭っていない自分がたまに登山や冒険のコメントを求められるたびに、そんなことを考えてしまう。
そして世の中全般的にみると、踏み込みが浅い人のほうが解説がうまかったりする。
いちばんの才能ってなんだろう
やっぱりやるかやらないか
頭脳明晰でシミュレーションや分析はすばらしいけれど、けっきょくやらずに終わる人の人生っていったいなんなんだろう
◇
きのう山でメモしたこと